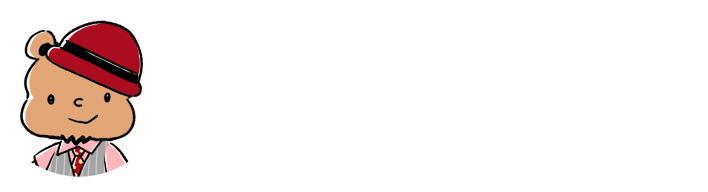練習するのが良いのか。
しなくても良いのか。
いや、そりゃ練習した方が良いのですよ。
ジャグリングの上達という意味で考えたら。
けれども、休むことによって
上手くなる(上手くなったと感じる)
ということは、あります。
問題は「休み方」です。
月に2回のジャグリング教室。
みんな、日常がありつつ、教室に通ってくれています。
練習時間が取れない事情もありましょうし、
そもそも「ジャグリングができるようになりたい」と思っていたとしても、「うまくなりたい!」というのが続ける主な理由になっているとは限りません。
ここら辺は深く聞いていないので、こうして考えてみると、聞いてみたいところではありますね。
さておき。
今日の教室のはじめには、
「練習できませんでした。」
というコメントが多かったのですが、
いざ始まってみると…
なんだかみんな調子が良い。
調子が良いと、練習にも熱を帯びてきます。
今日は、とても充実した時間になったように思います。
なんで調子が良かったのでしょうか。
先に「みんな」と書きましたが、しっかりと練習を重ねていて、その成果が実りつつあるひともいました。
これからが楽しみです。
一方で、さまざまな理由で、実際に練習ができなかったひともいます。
そんなひとの過去の練習を振り返ってみると、毎回課題を明確にしてポイントを一つに絞って練習をしてきたなぁ、と思いました。
学習は即効性があるわけではありません。
自分が練習をした時や、ひとにジャグリングを伝えたりする中で、学習の効果は、時間を経てからだにあらわれるものなんだなと感じています。
練習の成果は適度な間隔を置くことで、効果が実感できる形になってあらわれます。
しかし、ここで疑問がわきます。
「適度な間隔」とは、なんでしょうか。
記憶の忘却曲線に依って
ジャグリングに初めて触れるひとには
「翌朝、少しでも良いのでジャグリングのことを思い出してください、できればやってみてください」
と伝えます。
しかし、ジャグリングを続けているひとには、事情はだいぶ変わるでしょう。
練習の成果が出るのには、時間がかかる。
練習を続けた成果が、ある日突然華開くこともありますが、いつまで経っても成果を感じられないこともある…というよりも続けるほどに、そんなことばかり。
もちろん、四六時中ジャグリングのことを考えて練習していられれば素晴らしいけれども、現実的ではありません。私もできない。そんな時は練習のモチベーションを保つのも難しい。
それでも。
コンスタントに練習するに越したことはない。
場合によっては、練習をしないのは下手になるのではという恐怖に変わることもある。
けれども、そこで思い切って休んでみる。
すると、上手くなったと感じることが、あります。
それまで練習したボーナスみたいなものでしょうか。
かといって練習しなければ、確実に感覚は鈍ります。
だから。
ポイントを絞って、集中して練習する。
そして、休む。
このサイクルを自分の生活習慣に合わせて掴んで習慣にする、これが上達には良いのではと思います。
今までいろんなひとを見てきましたが、かかる時間はそれぞれにしろ、上手くなるひとはこれができています。
もちろん、上達だけがジャグリングの楽しみではないのですが、上達はジャグリングの楽しみの大きな部分を占める場合が多いので、ぜひ自分の生活に合った上達ペースを掴んで欲しいな、と思います。
上達が目標であれ、そうでないにしても、上手くなった!と感じる瞬間は嬉しいものです。
ジャグリングに喜びがありますように。
しんのすけ 武蔵境ジャグリング教室
毎月第一、三火曜日 19:00-20:30
セブンカルチャークラブ武蔵境
にて開講しています。
ジャグリングにご興味ありましたら、ぜひご連絡ください。
>> shinnnosuke.hp@gmail.com